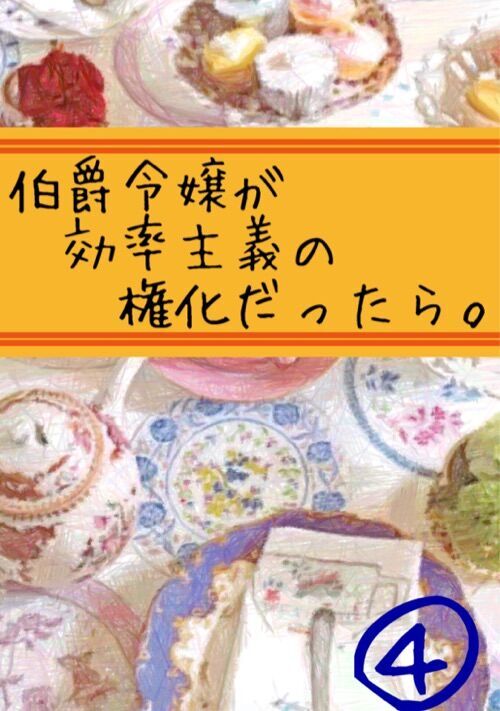37 / 63
セシリア、第2王子と初バトル
第5話 俺の主人は、面倒に愛されている(1)
しおりを挟むもしもセシリアが懇意にしていない相手に同じ問いを投げかけられたとしたら、ゼルゼンはきっとすまし顔で「いいえ、そのような事は何も」と答えただろう。
これはあくまで『セシリアが互いに緊張しない交友関係を結びたい』と思っている相手だからこその対応だ。
しかしそれは、必ずしも本音そのままではない。
ゼルゼンの本音は「いやもうホントにセシリアは一体何をしでかすか分からなくて、片時だって目が離せない」だ。
これを言わなかったのは『相手が貴族で自分はあくまでも使用人』という線引を忘れずにいたからこそ。
そして。
(俺はセシリア付き、コイツのフォローをすべき立場なんだから警戒するに越したことはない)
セシリアの目と判断は信じてる。
しかしそれでも何がトラブルに発展するか分からないのが人間関係というものだ。
主人をいつでもすぐにフォローできるようにするためには、どうしたって一定の警戒が必要になる。
そしてそれは、セシリアが警戒していないからこそ大切な役割になりうるのだ。
そもそも突発的なアレコレを前にして、残念ながらゼルゼンにはセシリアほどの立ち回りはできないだろう。
だから常に最悪を想定して不測の事態に備えるのも、彼の重要な仕事の内の一つである。
それもこれも、全ては。
(面倒事を嫌いながらも、何かと面倒事が寄ってくるからなぁー)
そう心の中で嘆くほどに、ゼルゼンの主人は面倒に愛される人物なのだから仕方がない。
そしてそんなゼルゼンの決して上辺だけではない返答に、どうやらレガシーは一定の好感を持ったようだった。
「セシリア嬢と共に居れば、これからは君と関わる事も増えそうだ。よろしくね、ゼルゼン」
そう言って、レガシーが控えめな微笑を向けてくる。
そんな彼にゼルゼンは、外面では平静を装いながらもその実安堵と喜びを胸の内に秘めていた。
「――勿体ないお言葉です。こちらこそ、宜しくお願い致します」
丁寧に執事の礼をとりながらそう告げて、ゆっくり頭を上げる。
すると、嬉しそうなレガシーの目とかち合った。
その目に、ゼルゼンは「人との付き合いが苦手なようだし、もしかすると彼は同年代の使用人と交流するのが初めてなのかもしれないな」と心の中で独り言ちる。
(じゃないと、貴族家の子息が一使用人との交流をこんなに喜ぶのは些か不自然だ)
なんて、思った時だった。
サクッという小さな音が聞こえ、視線をそちらへとやる。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
204
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる