17 / 28
17 皇帝の妻で聖女で
しおりを挟む
「……今の婚約者のためにリゼットを追い出したというのはデマだと?」
「そうです。リゼットが私の婚約者だったことはありませんから」
「では、なぜリゼットを追い出した?」
言葉が通じないことに苛立つように、パトリックはため息をつく。
「先ほども言ったではないですか。追い出してはいないと。聖女が行方不明になったのです。ああ、リゼットはもしかしたら私と婚約を望んでいて、それが叶わないと知って国を出て行ってしまったのかもしれませんが……それだったらすまない。しかし、祖国を見捨てて行くのはひどい。自分でもわかっているだろう?」
パトリックの視線が、リゼットに向けられ、諌めるように言った。
リゼットはカッとなってディーの腕に爪を立てた。繋いでいた手が離れる。
しかし飛びかかる前に、今度は腰にたくましい腕が回された。リゼットはその腕から逃れられず、しかし気持ちは高ぶって、声を荒げて吐き捨てた。
「ふざけないで! そっちが私を捨てたんでしょう。 ユリさんを聖女にしたかったのか、結婚したかったのか知らないけど、私を偽物扱いして国から追い出したくせに」
一瞬驚いたような顔をしたパトリックは、すぐに哀れむかのような視線を寄越す。
「どうしてそんなことを言うんだ? 事実無根だ。証拠がないだろう? まさか、皇帝陛下は彼女の戯言を信じたのですか?」
パトリックが馬鹿にするかのように、鼻を鳴らす。
「このっ!」
とびかかりそうな勢いのリゼットの腰を、ディーはつかんで離さない。
バタバタと暴れるが、それも力ずくで抑えられてしまう。口を開いて罵しろうとすれば、その口をディーの方手が覆った。
かろうじてリゼットはパトリックを口汚くののしることなく済んでいた。ディーがいなければ、今にも掴みかかっていただろう。聖女のイメージダウンも著しいことになりかねないので感謝すべきところだが、リゼットは荒ぶる気持ちを無理やり抑えることができずに、ディーに苛立ちをぶつけるように腕に爪をたてる。
「あなたの言葉にも証拠はないだろうが」
人目を憚らず暴れるリゼットを押さえつけるディーは、低い声で囁くように言った。
「王族である私の言葉こそが証拠です。聖女が言うよりずっと説得力があるでしょう?」
「……本気で言っているのか」
ディーはさらに声を低くして尋ねた。
帝国では、聖女の力はある意味絶対だ。
なんといっても神が愛した存在なのだから。何も力を持たない王族よりも、神に愛された聖女を民が信じるのは、当たり前と言える。
聖女の言葉に国が左右されることすらある。だからこその王族との婚姻なのだ。聖女を制御している。ということを形だけでも民に見せるため。
そうしなければならないほど、聖女の言葉には力があるということである。
王族が黒といっても、聖女が白と言えば覆ることすらある。そういう時代だ。
それは本来アルサンテでも同じ。同じ目的で聖女を王族と婚姻させるという風習ができていたはずだが。しかし、パトリックはそうは思っていないのだ。
「あたりまえでしょう?」
不思議そうに、パトリックは首を傾げた。
「聖女の言葉がどれほど力があっても、王族の言葉はもっと力がありますよ。聖女が黒といっても、我々王族が白と言えば白になる。当然のことでしょう?」
パトリックは不思議そうに言った。
「話にならない」
ディーは小さくため息をつく。
今回のことも、民に知られれば民はリゼットを推すだろう。
しかもパトリックは他国の王子だ。信じる理由は何もない。
「王族が言ったから証拠になる? だから聖女が言ってることは嘘だ? そんな常識知らずな言葉を真に受けてリゼットをそちらへ渡すと本気でお思いか?」
「常識知らず? 当然のことでは?」
「馬鹿な……。聖女の言葉こそ信じる。それが我が国だ。あなたが、いや、そちらの国がどうであれ、我が帝国ではそれこそが真実。証拠もないあなたの言葉を信じる理由がない」
ディーが言い切ると、パトリックはおかしなものでも見るような目でディーを見つめた。それが不敬だと思ってもいないようだ。彼は一国の王子だが、相手は大陸一の帝国の王。さてどちらに力があるかなど一目瞭然。のはずなのだが。
「王族より? 聖女? 不思議なことをおっしゃるのですね。聖女は王族のものではないですか」
「ものか……ならばこういう言い方なら納得するか?」
ディーはリゼットの腰を再び強く抱きしめると、リゼットの握りしめられていた手を取って、指を絡めた。
するりと絡みつくような指に、びくりとリゼットが震える。リゼットの手をさらに強く握って、ディーはうっすらと笑った。
「俺の次期皇后の言葉を、俺は信じる」
一瞬、沈黙。
その後、わっと声が上がった。
それは歓声に近かった。
長らく発表されていなかった、しかしいずれ必ずそうなると信じられていた、皇帝と聖女の結婚。それが今、皇帝の口から飛び出したのだ。
リゼットは茫然とディーを見上げた。
ずっと高いところにある瞳が、一瞬リゼットを見下ろし、すぐにパトリックに向けられる。
「そうです。リゼットが私の婚約者だったことはありませんから」
「では、なぜリゼットを追い出した?」
言葉が通じないことに苛立つように、パトリックはため息をつく。
「先ほども言ったではないですか。追い出してはいないと。聖女が行方不明になったのです。ああ、リゼットはもしかしたら私と婚約を望んでいて、それが叶わないと知って国を出て行ってしまったのかもしれませんが……それだったらすまない。しかし、祖国を見捨てて行くのはひどい。自分でもわかっているだろう?」
パトリックの視線が、リゼットに向けられ、諌めるように言った。
リゼットはカッとなってディーの腕に爪を立てた。繋いでいた手が離れる。
しかし飛びかかる前に、今度は腰にたくましい腕が回された。リゼットはその腕から逃れられず、しかし気持ちは高ぶって、声を荒げて吐き捨てた。
「ふざけないで! そっちが私を捨てたんでしょう。 ユリさんを聖女にしたかったのか、結婚したかったのか知らないけど、私を偽物扱いして国から追い出したくせに」
一瞬驚いたような顔をしたパトリックは、すぐに哀れむかのような視線を寄越す。
「どうしてそんなことを言うんだ? 事実無根だ。証拠がないだろう? まさか、皇帝陛下は彼女の戯言を信じたのですか?」
パトリックが馬鹿にするかのように、鼻を鳴らす。
「このっ!」
とびかかりそうな勢いのリゼットの腰を、ディーはつかんで離さない。
バタバタと暴れるが、それも力ずくで抑えられてしまう。口を開いて罵しろうとすれば、その口をディーの方手が覆った。
かろうじてリゼットはパトリックを口汚くののしることなく済んでいた。ディーがいなければ、今にも掴みかかっていただろう。聖女のイメージダウンも著しいことになりかねないので感謝すべきところだが、リゼットは荒ぶる気持ちを無理やり抑えることができずに、ディーに苛立ちをぶつけるように腕に爪をたてる。
「あなたの言葉にも証拠はないだろうが」
人目を憚らず暴れるリゼットを押さえつけるディーは、低い声で囁くように言った。
「王族である私の言葉こそが証拠です。聖女が言うよりずっと説得力があるでしょう?」
「……本気で言っているのか」
ディーはさらに声を低くして尋ねた。
帝国では、聖女の力はある意味絶対だ。
なんといっても神が愛した存在なのだから。何も力を持たない王族よりも、神に愛された聖女を民が信じるのは、当たり前と言える。
聖女の言葉に国が左右されることすらある。だからこその王族との婚姻なのだ。聖女を制御している。ということを形だけでも民に見せるため。
そうしなければならないほど、聖女の言葉には力があるということである。
王族が黒といっても、聖女が白と言えば覆ることすらある。そういう時代だ。
それは本来アルサンテでも同じ。同じ目的で聖女を王族と婚姻させるという風習ができていたはずだが。しかし、パトリックはそうは思っていないのだ。
「あたりまえでしょう?」
不思議そうに、パトリックは首を傾げた。
「聖女の言葉がどれほど力があっても、王族の言葉はもっと力がありますよ。聖女が黒といっても、我々王族が白と言えば白になる。当然のことでしょう?」
パトリックは不思議そうに言った。
「話にならない」
ディーは小さくため息をつく。
今回のことも、民に知られれば民はリゼットを推すだろう。
しかもパトリックは他国の王子だ。信じる理由は何もない。
「王族が言ったから証拠になる? だから聖女が言ってることは嘘だ? そんな常識知らずな言葉を真に受けてリゼットをそちらへ渡すと本気でお思いか?」
「常識知らず? 当然のことでは?」
「馬鹿な……。聖女の言葉こそ信じる。それが我が国だ。あなたが、いや、そちらの国がどうであれ、我が帝国ではそれこそが真実。証拠もないあなたの言葉を信じる理由がない」
ディーが言い切ると、パトリックはおかしなものでも見るような目でディーを見つめた。それが不敬だと思ってもいないようだ。彼は一国の王子だが、相手は大陸一の帝国の王。さてどちらに力があるかなど一目瞭然。のはずなのだが。
「王族より? 聖女? 不思議なことをおっしゃるのですね。聖女は王族のものではないですか」
「ものか……ならばこういう言い方なら納得するか?」
ディーはリゼットの腰を再び強く抱きしめると、リゼットの握りしめられていた手を取って、指を絡めた。
するりと絡みつくような指に、びくりとリゼットが震える。リゼットの手をさらに強く握って、ディーはうっすらと笑った。
「俺の次期皇后の言葉を、俺は信じる」
一瞬、沈黙。
その後、わっと声が上がった。
それは歓声に近かった。
長らく発表されていなかった、しかしいずれ必ずそうなると信じられていた、皇帝と聖女の結婚。それが今、皇帝の口から飛び出したのだ。
リゼットは茫然とディーを見上げた。
ずっと高いところにある瞳が、一瞬リゼットを見下ろし、すぐにパトリックに向けられる。
24
あなたにおすすめの小説

聖女の力を妹に奪われ魔獣の森に捨てられたけど、何故か懐いてきた白狼(実は呪われた皇帝陛下)のブラッシング係に任命されました
AK
恋愛
「--リリアナ、貴様との婚約は破棄する! そして妹の功績を盗んだ罪で、この国からの追放を命じる!」
公爵令嬢リリアナは、腹違いの妹・ミナの嘘によって「偽聖女」の汚名を着せられ、婚約者の第二王子からも、実の父からも絶縁されてしまう。 身一つで放り出されたのは、凶暴な魔獣が跋扈する北の禁足地『帰らずの魔の森』。
死を覚悟したリリアナが出会ったのは、伝説の魔獣フェンリル——ではなく、呪いによって巨大な白狼の姿になった隣国の皇帝・アジュラ四世だった!
人間には効果が薄いが、動物に対しては絶大な癒やし効果を発揮するリリアナの「聖女の力」。 彼女が何気なく白狼をブラッシングすると、苦しんでいた皇帝の呪いが解け始め……?
「余の呪いを解くどころか、極上の手触りで撫でてくるとは……。貴様、責任を取って余の専属ブラッシング係になれ」
こうしてリリアナは、冷徹と恐れられる氷の皇帝(中身はツンデレもふもふ)に拾われ、帝国で溺愛されることに。 豪華な離宮で美味しい食事に、最高のもふもふタイム。虐げられていた日々が嘘のような幸せスローライフが始まる。
一方、本物の聖女を追放してしまった祖国では、妹のミナが聖女の力を発揮できず、大地が枯れ、疫病が蔓延し始めていた。 元婚約者や父が慌ててミレイユを連れ戻そうとするが、時すでに遅し。 「私の主人は、この可愛い狼様(皇帝陛下)だけですので」 これは、すべてを奪われた令嬢が、最強のパートナーを得て幸せになり、自分を捨てた者たちを見返す逆転の物語。

氷の王弟殿下から婚約破棄を突き付けられました。理由は聖女と結婚するからだそうです。
吉川一巳
恋愛
ビビは婚約者である氷の王弟イライアスが大嫌いだった。なぜなら彼は会う度にビビの化粧や服装にケチをつけてくるからだ。しかし、こんな婚約耐えられないと思っていたところ、国を揺るがす大事件が起こり、イライアスから神の国から召喚される聖女と結婚しなくてはいけなくなったから破談にしたいという申し出を受ける。内心大喜びでその話を受け入れ、そのままの勢いでビビは神官となるのだが、招かれた聖女には問題があって……。小説家になろう、カクヨムにも投稿しています。

(完結)お荷物聖女と言われ追放されましたが、真のお荷物は追放した王太子達だったようです
しまうま弁当
恋愛
伯爵令嬢のアニア・パルシスは婚約者であるバイル王太子に突然婚約破棄を宣言されてしまうのでした。
さらにはアニアの心の拠り所である、聖女の地位まで奪われてしまうのでした。
訳が分からないアニアはバイルに婚約破棄の理由を尋ねましたが、ひどい言葉を浴びせつけられるのでした。
「アニア!お前が聖女だから仕方なく婚約してただけだ。そうでなけりゃ誰がお前みたいな年増女と婚約なんかするか!!」と。
アニアの弁明を一切聞かずに、バイル王太子はアニアをお荷物聖女と決めつけて婚約破棄と追放をさっさと決めてしまうのでした。
挙句の果てにリゼラとのイチャイチャぶりをアニアに見せつけるのでした。
アニアは妹のリゼラに助けを求めましたが、リゼラからはとんでもない言葉が返ってきたのでした。
リゼラこそがアニアの追放を企てた首謀者だったのでした。
アニアはリゼラの自分への悪意を目の当たりにして愕然しますが、リゼラは大喜びでアニアの追放を見送るのでした。
信じていた人達に裏切られたアニアは、絶望して当てもなく宿屋生活を始めるのでした。
そんな時運命を変える人物に再会するのでした。
それはかつて同じクラスで一緒に学んでいた学友のクライン・ユーゲントでした。
一方のバイル王太子達はアニアの追放を喜んでいましたが、すぐにアニアがどれほどの貢献をしていたかを目の当たりにして自分達こそがお荷物であることを思い知らされるのでした。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
全25話執筆済み 完結しました

偽りの断罪で追放された悪役令嬢ですが、実は「豊穣の聖女」でした。辺境を開拓していたら、氷の辺境伯様からの溺愛が止まりません!
黒崎隼人
ファンタジー
「お前のような女が聖女であるはずがない!」
婚約者の王子に、身に覚えのない罪で断罪され、婚約破棄を言い渡された公爵令嬢セレスティナ。
罰として与えられたのは、冷酷非情と噂される「氷の辺境伯」への降嫁だった。
それは事実上の追放。実家にも見放され、全てを失った――はずだった。
しかし、窮屈な王宮から解放された彼女は、前世で培った知識を武器に、雪と氷に閉ざされた大地で新たな一歩を踏み出す。
「どんな場所でも、私は生きていける」
打ち捨てられた温室で土に触れた時、彼女の中に眠る「豊穣の聖女」の力が目覚め始める。
これは、不遇の令嬢が自らの力で運命を切り開き、不器用な辺境伯の凍てついた心を溶かし、やがて世界一の愛を手に入れるまでの、奇跡と感動の逆転ラブストーリー。
国を捨てた王子と偽りの聖女への、最高のざまぁをあなたに。

【完結】大聖女は無能と蔑まれて追放される〜殿下、1%まで力を封じよと命令したことをお忘れですか?隣国の王子と婚約しましたので、もう戻りません
冬月光輝
恋愛
「稀代の大聖女が聞いて呆れる。フィアナ・イースフィル、君はこの国の聖女に相応しくない。職務怠慢の罪は重い。無能者には国を出ていってもらう。当然、君との婚約は破棄する」
アウゼルム王国の第二王子ユリアンは聖女フィアナに婚約破棄と国家追放の刑を言い渡す。
フィアナは侯爵家の令嬢だったが、両親を亡くしてからは教会に預けられて類稀なる魔法の才能を開花させて、その力は大聖女級だと教皇からお墨付きを貰うほどだった。
そんな彼女は無能者だと追放されるのは不満だった。
なぜなら――
「君が力を振るうと他国に狙われるし、それから守るための予算を割くのも勿体ない。明日からは能力を1%に抑えて出来るだけ働くな」
何を隠そう。フィアナに力を封印しろと命じたのはユリアンだったのだ。
彼はジェーンという国一番の美貌を持つ魔女に夢中になり、婚約者であるフィアナが邪魔になった。そして、自らが命じたことも忘れて彼女を糾弾したのである。
国家追放されてもフィアナは全く不自由しなかった。
「君の父親は命の恩人なんだ。私と婚約してその力を我が国の繁栄のために存分に振るってほしい」
隣国の王子、ローレンスは追放されたフィアナをすぐさま迎え入れ、彼女と婚約する。
一方、大聖女級の力を持つといわれる彼女を手放したことがバレてユリアンは国王陛下から大叱責を食らうことになっていた。

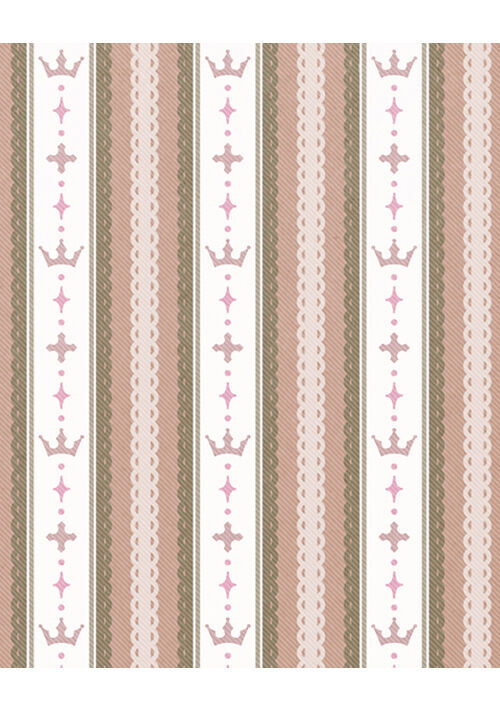
【完結】「神様、辞めました〜竜神の愛し子に冤罪を着せ投獄するような人間なんてもう知らない」
まほりろ
恋愛
王太子アビー・シュトースと聖女カーラ・ノルデン公爵令嬢の結婚式当日。二人が教会での誓いの儀式を終え、教会の扉を開け外に一歩踏み出したとき、国中の壁や窓に不吉な文字が浮かび上がった。
【本日付けで神を辞めることにした】
フラワーシャワーを巻き王太子と王太子妃の結婚を祝おうとしていた参列者は、突然現れた文字に驚きを隠せず固まっている。
国境に壁を築きモンスターの侵入を防ぎ、結界を張り国内にいるモンスターは弱体化させ、雨を降らせ大地を潤し、土地を豊かにし豊作をもたらし、人間の体を強化し、生活が便利になるように魔法の力を授けた、竜神ウィルペアトが消えた。
人々は三カ月前に冤罪を着せ、|罵詈雑言《ばりぞうごん》を浴びせ、石を投げつけ投獄した少女が、本物の【竜の愛し子】だと分かり|戦慄《せんりつ》した。
「Copyright(C)2021-九頭竜坂まほろん」
アルファポリスに先行投稿しています。
表紙素材はあぐりりんこ様よりお借りしております。
2021/12/13、HOTランキング3位、12/14総合ランキング4位、恋愛3位に入りました! ありがとうございます!

「無能な妻」と蔑まれた令嬢は、離婚後に隣国の王子に溺愛されました。
腐ったバナナ
恋愛
公爵令嬢アリアンナは、魔力を持たないという理由で、夫である侯爵エドガーから無能な妻と蔑まれる日々を送っていた。
魔力至上主義の貴族社会で価値を見いだされないことに絶望したアリアンナは、ついに離婚を決断。
多額の慰謝料と引き換えに、無能な妻という足枷を捨て、自由な平民として辺境へと旅立つ。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















