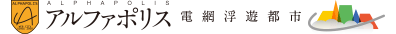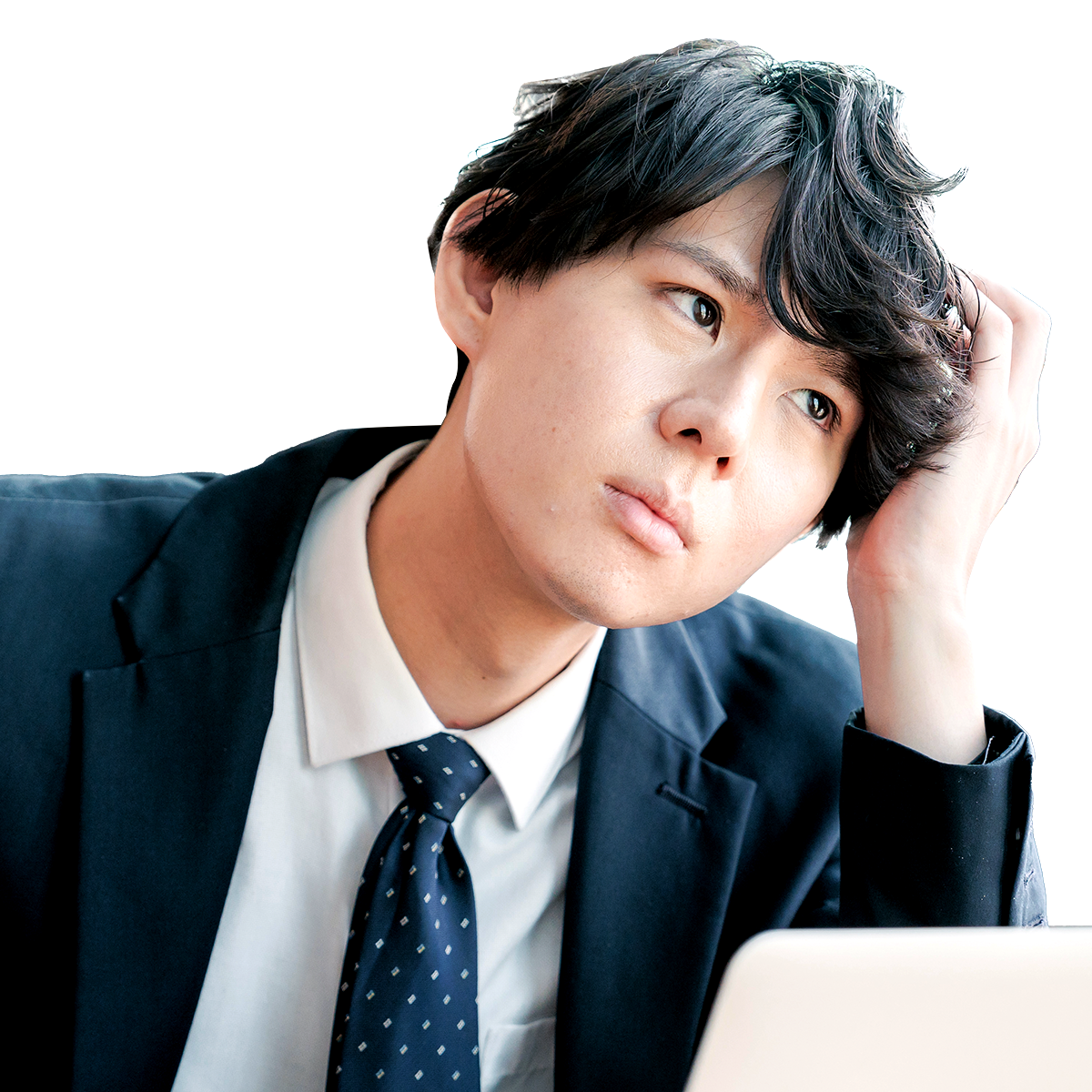多くの親がわかってない「子どものやる気を引き出す」簡単な方法

子どもにやる気になってもらうのは不可能?
子どもに、目標に向かってがんばれる人になってほしい、と願うのは親ならばだれしも望むことでしょう。
子どもが自分で、
「速く泳げるようになりたい」
「勉強できるようになりたい」
「将来は〇〇になりたい」
こんなふうに具体的な目標を持ち、それに向かって努力してくれるようになってくれたらどんなに嬉しいか。
しかし、そうなってくれることは稀でしょう。
むしろ子どもは、身近にあるエンタメにズブズブとハマっていき、
「テレビ観たい」
「YouTube観たい」
「ゲームしたい」
四六時中、そう口にするようになるものです。
そんな子どもに、エンタメをいくらでも楽しめてしまうスマホを買い与えようものなら、平気で何時間も熱中してしまうでしょう。
親が「勉強したら?」などと提案しても、空返事されるのがオチです。
スマホはどこまで脳を壊すか
それほど子どもを夢中にさせてしまうスマホですが、便利な一方で、とても怖い一面があります。
以前『スマホはどこまで脳を壊すか』(著・榊浩平、川島隆太/朝日新聞出版)という新書が話題になりましたが、この本にとても衝撃的なことが書いてありました。スマホの使用時間と学業の成績には相関関係があり、スマホの使用時間が増えると成績が落ちるというのです。
たとえば、平日1日あたりのスマホ使用時間とテストの成績の関係を調べてみると、スマホの使用時間が1日に1時間未満の子が偏差値50以上だったのに対し、4時間以上スマホを使用していた子は偏差値40程度まで落ちていました。
もう一歩踏み込んで、家庭での学習時間とスマホの使用時間を合わせて見てみると、さらに恐ろしい結果が明らかになります。
学習時間が増えれば学力が上がるのは当然だと思いますが、学習時間を増やしたところで、スマホを一定の時間以上使用してしまうと、その学習時間の効果が打ち消されてしまうというのです。
具体的なデータを一つ取りあげてみましょう。1日2時間勉強し、さらにスマホを3時間使用した子がいたとします。1日のうちにそれくらいの時間スマホをさわってしまう子は少なくないと思いますが、そうした子の数学のテストの点数はあまりふるわなかったそうです。それどころか、勉強をまったくしないスマホ不使用の子たちの成績さえ下回ったというのです。
なぜそんなことが起きてしまうのか。それは、「スマホの使用が脳に悪影響を与えたからだ」と考えられるそうです。
スマホの長時間使用が、脳の前頭前野という、読み書き・計算など勉強に使う「認知機能」を担当し、さらに実行機能や会話など「非認知力」の機能も担当する部分に、著しく悪い影響を与えてしまうのです。
なお、スマホの長時間利用していた子どもが長時間利用をやめると、ちゃんと成績が伸びることもわかっています。
脳に楽をさせると、考えない子どもになっていく
調べものをする際に、紙の辞書などを使わず、ネットで済ませてしまうことも、脳にとってはあまりよいことではないようです。
前頭前野の活動を調べると、スマホで調べているときは、左脳も右脳もあまり活動が増えません。ところが紙の辞書で調べると、左脳も右脳も一気に活動量が増えるのです。
私たちの脳はものすごくエネルギーを使う臓器なので、なるべく省エネをしようとするのだそうです。そのためか、本来脳が行うべきさまざまな労力を省いてくれるスマホで調べものをすると、脳は「覚えなくていい」「考えなくていい」と勝手に判断し、省エネに走ってしまうそうです。そうして、結果的に脳の活動量が減り、発達が弱くなってしまう、というメカニズムのようです。
筋肉は、トレーニングをサボり、楽をすればするほど衰えていきますが、脳も同じことが言えます。
脳に楽をさせる環境を用意して、ただスマホをいじる、YouTubeを観る、ということをしていると、私たちの脳はどんどん楽をするようになり、自分で考えることをやめ、ついには、やりたいことがない、無気力な人間へと流されてしまうわけです。
これは、子育てだけでなく、私たちビジネスマンにも関係する問題でしょう。
チャットGPTに聞けば答えが出てくる時代です。若者たちは易々と使いこなし、アイデアが出てこないときには、チャットGPTにアイデアを求め、出てきた意見に「おー、いいじゃん」と歓声を上げ、その選択肢から選ぶ。
答えを早く求める風潮が、古い世代が若い頃に大切にしてきた「脳で汗をかく」という経験を奪い、脳に楽をさせてしまう。その結果、徐々に私たちの「自分で考える力」を奪っているように感じるのは私の杞憂でしょうか。
オススメ記事
「「家族」というチームのつくり方」 記事一覧
- 第29回 心配性の奥さんが笑顔になる、すごい会話術
- 第30回 ピリピリ妻が別人のようにやさしくなる、すごい会話術
- 第12回 多くの親がわかってない「子どものやる気を引き出す」簡単な方法
- 第11回 「わが子を東大生にする」ために親がすべきたった一つのこと
- 第10回 子どもの「将来の年収を増やす」カンタンな接し方