子檀嶺城始末―こまゆみじょうしまつ―
「真田対徳川なら絶対に徳川が勝つに決まってるから真田は見限る。でも徳川軍の一員として戦場に出て痛い思いをするのはまっぴら御免。だから『徳川に味方する宣言』だけしておいて、終戦まで主戦場から離れた山城に引きこもる作戦」
を実行に移した杉原四郎兵衛。
ところが、戦から半月ほど経過したのに「勝ったはずの徳川」からの使者が来ない。
それもそのはず。実は徳川軍はあっさり負けてしまっていたのだ!
やがて、四郎兵衛たちの籠もる山城に、真田の若殿が率いる一軍が迫り来る。
兵糧もやる気も尽きた四郎兵衛たちの運命や如何に。
----------✂----------
※今作は、旧作【子檀嶺城戦記】をリライトしたものとなります。
旧作をお読みいただいた皆様も、改めてご一読いただければ幸いです。
----------✂----------
真田昌幸が「占拠」する信州上田城へ向かって、徳川軍が攻め寄せる。
上州沼田の領有権争いから持ち上がった真田と徳川(&北条)の闘争は、真田の本拠地での大規模戦闘に発展した。
昌幸の嫡男・源三郎信幸は、父に命じられた通りに伏兵部隊を率いて支城へ詰めた。
同じ頃、二十名ほどの男たちが、主戦場から遠く離れた子檀嶺(こまゆみ)岳の古城に入った。塩田平の地侍・杉原四郎兵衛の一党である。
真田と徳川の圧倒的戦力差から徳川軍が勝つと予想した四郎兵衛は、
「徳川に身方する」
と吹聴しつつも古城からは一歩たりとも出ず、
「勝利するであろう徳川軍からの勧誘」
を待つという消極的策戦を取ったのだった。
しかし半月が過ぎても、徳川からの迎えは現れない。
それもそのはずで、真田勢に敗れた徳川勢は、すでに東信濃から撤退済みだった!
廃城で孤立し、事態を知る手段もなく、不安に苛まれる四郎兵衛に耳に、銃声が聞こえた――。
天正十三年(1585)閏八月。
後の世に、第一次上田合戦と呼ばれる戦の裏側で起きた、ほんの数日間の「反乱」の顛末。
を実行に移した杉原四郎兵衛。
ところが、戦から半月ほど経過したのに「勝ったはずの徳川」からの使者が来ない。
それもそのはず。実は徳川軍はあっさり負けてしまっていたのだ!
やがて、四郎兵衛たちの籠もる山城に、真田の若殿が率いる一軍が迫り来る。
兵糧もやる気も尽きた四郎兵衛たちの運命や如何に。
----------✂----------
※今作は、旧作【子檀嶺城戦記】をリライトしたものとなります。
旧作をお読みいただいた皆様も、改めてご一読いただければ幸いです。
----------✂----------
真田昌幸が「占拠」する信州上田城へ向かって、徳川軍が攻め寄せる。
上州沼田の領有権争いから持ち上がった真田と徳川(&北条)の闘争は、真田の本拠地での大規模戦闘に発展した。
昌幸の嫡男・源三郎信幸は、父に命じられた通りに伏兵部隊を率いて支城へ詰めた。
同じ頃、二十名ほどの男たちが、主戦場から遠く離れた子檀嶺(こまゆみ)岳の古城に入った。塩田平の地侍・杉原四郎兵衛の一党である。
真田と徳川の圧倒的戦力差から徳川軍が勝つと予想した四郎兵衛は、
「徳川に身方する」
と吹聴しつつも古城からは一歩たりとも出ず、
「勝利するであろう徳川軍からの勧誘」
を待つという消極的策戦を取ったのだった。
しかし半月が過ぎても、徳川からの迎えは現れない。
それもそのはずで、真田勢に敗れた徳川勢は、すでに東信濃から撤退済みだった!
廃城で孤立し、事態を知る手段もなく、不安に苛まれる四郎兵衛に耳に、銃声が聞こえた――。
天正十三年(1585)閏八月。
後の世に、第一次上田合戦と呼ばれる戦の裏側で起きた、ほんの数日間の「反乱」の顛末。
一
二
三
四
五
六
七
八
あなたにおすすめの小説

与兵衛長屋つれあい帖 お江戸ふたり暮らし
かずえ
歴史・時代
旧題:ふたり暮らし
長屋シリーズ一作目。
第八回歴史・時代小説大賞で優秀短編賞を頂きました。応援してくださった皆様、ありがとうございます。
十歳のみつは、十日前に一人親の母を亡くしたばかり。幸い、母の蓄えがあり、自分の裁縫の腕の良さもあって、何とか今まで通り長屋で暮らしていけそうだ。
頼まれた繕い物を届けた帰り、くすんだ着物で座り込んでいる男の子を拾う。
一人で寂しかったみつは、拾った男の子と二人で暮らし始めた。

大奥~牡丹の綻び~
翔子
歴史・時代
*この話は、もしも江戸幕府が永久に続き、幕末の流血の争いが起こらず、平和な時代が続いたら……と想定して書かれたフィクションとなっております。
大正時代・昭和時代を省き、元号が「平成」になる前に候補とされてた元号を使用しています。
映像化された数ある大奥関連作品を敬愛し、踏襲して書いております。
リアルな大奥を再現するため、性的描写を用いております。苦手な方はご注意ください。
時は17代将軍の治世。
公家・鷹司家の姫宮、藤子は大奥に入り御台所となった。
京の都から、慣れない江戸での生活は驚き続きだったが、夫となった徳川家正とは仲睦まじく、百鬼繚乱な大奥において幸せな生活を送る。
ところが、時が経つにつれ、藤子に様々な困難が襲い掛かる。
祖母の死
鷹司家の断絶
実父の突然の死
嫁姑争い
姉妹間の軋轢
壮絶で波乱な人生が藤子に待ち構えていたのであった。
2023.01.13
修正加筆のため一括非公開
2023.04.20
修正加筆 完成
2023.04.23
推敲完成 再公開
2023.08.09
「小説家になろう」にも投稿開始。

【完結】ふたつ星、輝いて 〜あやし兄弟と町娘の江戸捕物抄〜
上杉
歴史・時代
■歴史小説大賞奨励賞受賞しました!■
おりんは江戸のとある武家屋敷で下女として働く14歳の少女。ある日、突然屋敷で母の急死を告げられ、自分が花街へ売られることを知った彼女はその場から逃げだした。
母は殺されたのかもしれない――そんな絶望のどん底にいたおりんに声をかけたのは、奉行所で同心として働く有島惣次郎だった。
今も刺客の手が迫る彼女を守るため、彼の屋敷で住み込みで働くことが決まる。そこで彼の兄――有島清之進とともに生活を始めるのだが、病弱という噂とはかけ離れた腕っぷしのよさに、おりんは驚きを隠せない。
そうしてともに生活しながら少しづつ心を開いていった――その矢先のことだった。
母の命を奪った犯人が発覚すると同時に、何故か兄清之進に凶刃が迫り――。
とある秘密を抱えた兄弟と町娘おりんの紡ぐ江戸捕物抄です!お楽しみください!
※フィクションです。
※周辺の歴史事件などは、史実を踏んでいます。
皆さまご評価頂きありがとうございました。大変嬉しいです!
今後も精進してまいります!

法隆寺燃ゆ
hiro75
歴史・時代
奴婢として、一生平凡に暮らしていくのだと思っていた………………上宮王家の奴婢として生まれた弟成だったが、時代がそれを許さなかった。上宮王家の滅亡、乙巳の変、白村江の戦………………推古天皇、山背大兄皇子、蘇我入鹿、中臣鎌足、中大兄皇子、大海人皇子、皇極天皇、孝徳天皇、有間皇子………………為政者たちの権力争いに巻き込まれていくのだが………………
正史の裏に隠れた奴婢たちの悲哀、そして権力者たちの愛憎劇、飛鳥を舞台にした大河小説がいまはじまる!!
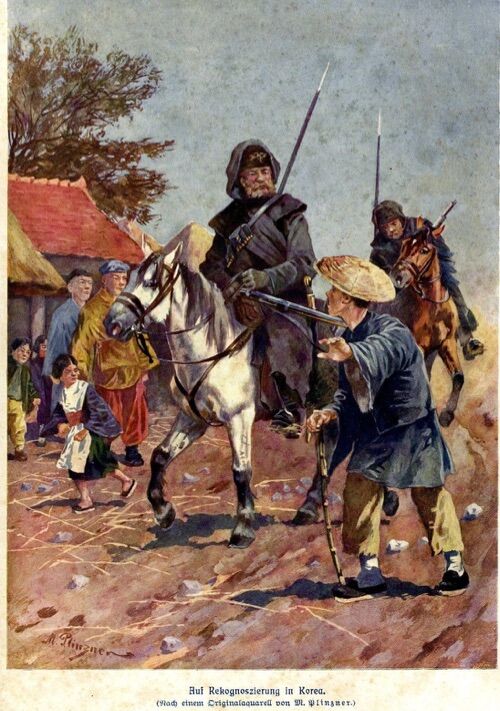
日露戦争の真実
蔵屋
歴史・時代
私の先祖は日露戦争の奉天の戦いで若くして戦死しました。
日本政府の定めた徴兵制で戦地に行ったのでした。
日露戦争が始まったのは明治37年(1904)2月6日でした。
帝政ロシアは清国の領土だった中国東北部を事実上占領下に置き、さらに朝鮮半島、日本海に勢力を伸ばそうとしていました。
日本はこれに対抗し開戦に至ったのです。
ほぼ同時に、日本連合艦隊はロシア軍の拠点港である旅順に向かい、ロシア軍の旅順艦隊の殲滅を目指すことになりました。
ロシア軍はヨーロッパに配備していたバルチック艦隊を日本に派遣するべく準備を開始したのです。
深い入り江に守られた旅順沿岸に設置された強力な砲台のため日本の連合艦隊は、陸軍に陸上からの旅順艦隊攻撃を要請したのでした。
この物語の始まりです。
『神知りて 人の幸せ 祈るのみ
神の伝えし 愛善の道』
この短歌は私が今年元旦に詠んだ歌である。
作家 蔵屋日唱

別れし夫婦の御定書(おさだめがき)
佐倉 蘭
歴史・時代
★第11回歴史・時代小説大賞 奨励賞受賞★
嫡男を産めぬがゆえに、姑の策略で南町奉行所の例繰方与力・進藤 又十蔵と離縁させられた与岐(よき)。
離縁後、生家の父の猛反対を押し切って生まれ育った八丁堀の組屋敷を出ると、小伝馬町の仕舞屋に居を定めて一人暮らしを始めた。
月日は流れ、姑の思惑どおり後妻が嫡男を産み、婚家に置いてきた娘は二人とも無事与力の御家に嫁いだ。
おのれに起こったことは綺麗さっぱり水に流した与岐は、今では女だてらに離縁を望む町家の女房たちの代わりに亭主どもから去り状(三行半)をもぎ取るなどをする「公事師(くじし)」の生業(なりわい)をして生計を立てていた。
されどもある日突然、与岐の仕舞屋にとっくの昔に離縁したはずの元夫・又十蔵が転がり込んできて——
※「今宵は遣らずの雨」「大江戸ロミオ&ジュリエット」「大江戸シンデレラ」「大江戸の番人 〜吉原髪切り捕物帖〜」にうっすらと関連したお話ですが単独でお読みいただけます。

本能寺からの決死の脱出 ~尾張の大うつけ 織田信長 天下を統一す~
bekichi
歴史・時代
戦国時代の日本を背景に、織田信長の若き日の物語を語る。荒れ狂う風が尾張の大地を駆け巡る中、夜空の星々はこれから繰り広げられる壮絶な戦いの予兆のように輝いている。この混沌とした時代において、信長はまだ無名であったが、彼の野望はやがて天下を揺るがすことになる。信長は、父・信秀の治世に疑問を持ちながらも、独自の力を蓄え、異なる理想を追求し、反逆者とみなされることもあれば期待の星と讃えられることもあった。彼の目標は、乱世を統一し平和な時代を創ることにあった。物語は信長の足跡を追い、若き日の友情、父との確執、大名との駆け引きを描く。信長の人生は、斎藤道三、明智光秀、羽柴秀吉、徳川家康、伊達政宗といった時代の英傑たちとの交流とともに、一つの大きな物語を形成する。この物語は、信長の未知なる野望の軌跡を描くものである。

世界はあるべき姿へ戻される 第二次世界大戦if戦記
颯野秋乃
歴史・時代
1929年に起きた、世界を巻き込んだ大恐慌。世界の大国たちはそれからの脱却を目指し、躍起になっていた。第一次世界大戦の敗戦国となったドイツ第三帝国は多額の賠償金に加えて襲いかかる恐慌に国の存続の危機に陥っていた。援助の約束をしたアメリカは恐慌を理由に賠償金の支援を破棄。フランスは、自らを救うために支払いの延期は認めない姿勢を貫く。
ドイツ第三帝国は自らの存続のために、世界に隠しながら軍備の拡張に奔走することになる。
また、極東の国大日本帝国。関係の悪化の一途を辿る日米関係によって受ける経済的打撃に苦しんでいた。
その解決法として提案された大東亜共栄圏。東南アジア諸国及び中国を含めた大経済圏、生存圏の構築に力を注ごうとしていた。
この小説は、ドイツ第三帝国と大日本帝国の2視点で進んでいく。現代では有り得なかった様々なイフが含まれる。それを楽しんで貰えたらと思う。
またこの小説はいかなる思想を賛美、賞賛するものでは無い。
この小説は現代とは似て非なるもの。登場人物は史実には沿わないので悪しからず…
大日本帝国視点は都合上休止中です。気分により再開するらもしれません。
【重要】
不定期更新。超絶不定期更新です。





















